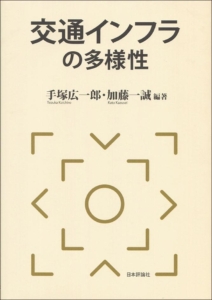2024.07.27
【レポート】(全4回)なぜ交通インフラ事業にプロジェクトファイナンスは難しいのかー第1回
2017.04.06 ナレッジ ハブ
1.はじめに(問題の所在と本稿の目的)
インフラストラクチャ(以下インフラ)向けの投融資に関心が高まっている。新興国ではインフラがまだまだ不足しており、欧米の先進国では既往のインフラが老朽化し刷新の機会を迎えている。インフラと一口に言っても、その範囲は広い。本稿では特に交通インフラに的を絞って考えていきたい。交通インフラとは具体的には道路、鉄道、橋梁、トンネル、港湾、空港などである。一般にインフラと言えば、交通インフラに加え電力や水の事業なども含まれるが、本稿ではインフラのうち交通インフラに限定して議論する。なぜなら、電力・水事業向けのプロジェクトファイナンスは既に多く成立しているからである。
プロジェクトファイナンスというファイナンス手法は事業そのものに融資する。プロジェクトファイナンスのレンダー(貸主。通常は銀行)は事業主体(通常特別目的会社)に対して出資者の債務保証を貰わずいわゆるノンリコースで融資する。プロジェクトファイナンスは事業リスクを取る融資である。現在世界のプロジェクトファイナンス市場の規模は約230億米ドル[*1](約25兆円)あるが、この市場を主導しているのは世界の民間銀行である。
[*1] Global Project Finance Review-Full Year 2016,Thomson Reuters
融資総額は大型案件では何千億円あるいは1兆円を超える。2012年国際石油開発帝石が主導する豪州液化天然ガス事業では200億米ドル(約2兆2千億円)の銀行融資をプロジェクトファイナンスの手法で調達した。プロジェクトファイナンスを活用することにより、大規模な金額の融資を実現している例は他にも多く存在する。従って、プロジェクトファイナンスの手法を交通インフラ事業の資金調達にもっと活用できないかという意見が出てくる。
電力・水事業向けのプロジェクトファイナンスが数多く成立している一方で、交通インフラ事業向けのプロジェクトファイナンスが成立している例は実は少ない。どうしてであろうか。その理由は交通インフラ事業の特性に起因していると考えられる。実際にプロジェクトファイナンスを行っているのはプロジェクトファイナンスを供与する銀行(以下、プロジェクトファイナンス・レンダー)であるので、プロジェクトファイナンス・レンダーの視点で交通インフラ事業の特性を見てゆくことが重要である。かれらが交通インフラ事業をどのように見ているのか、どうすれば交通インフラ事業にプロジェクトファイナンスが活用できるのか、こういった点を明らかにするのが本稿の目的である。
本稿ではまず交通インフラ事業の特性を4点採り上げ、それぞれの内容を子細に見てゆく。次にそれぞれの特性に対するプロジェクトファイナンス成立のための条件を考えてゆく。
次ページ 交通インフラ事業の特性